

 アードレー家の祖先はスコットランド人
アードレー家の祖先はスコットランド人
アードレー家の祖先について、マンガ・小説とも先代から前はほとんど描写がありません。とりあえず、マンガや小説に出てきたアードレー家の家風・伝統・祖先につながりそうな描写をまとめてみました。
[ 重要 / ※は管理人コメント(ひとりごと)]
【マンガ】
- ラガン家の運転手スチュアートのセリフ
「アードレーさまの土地はみんなすてきですよ このあたり一帯の土地をおもちのかたです。ラガン家もアードレーの一族で...みなさまスコットランド系です」
- 「アードレー家の総長がこのあたりに引っ越してくるらしいわ」「エルロイ大おばさまといってとてもこわいかたらしいわよ」
- アードレー家の正装はスコットランドの民族衣装
イライザ 「入り口にみんな正装してまってるわ」
(※アンソニー・ステア・アーチー以外の親族はスコットランドの民族衣装は着ていない。小説にはアードレー家のパーティでは子供が着るとある。大人で着ている人がいたので良く見てみると、どうも「執事」らしい)
-
レイクウッドのアードレー家の別荘
3階にあるシルクハットをかぶったろう人形には、アードレー家の先祖の名前がついている。
(※19世紀半ばのリンカーン時代にはやった「シルクハット・単眼鏡・マント」は上流階級の紳士をイメージさせる)
- 「ぼくらのいる別荘のような屋敷なんて二十ちかくもっているんだ・・・外国にもいくつかあるし・・・」
- ラガン夫人 「エルロイ大おばさまは作法にきびしいかたですからね」
- アードレー家の紋章バッジ
アンソニー 「そのバッジはねアードレー家の男子がもつものなんだよ」
(※小説の第3部では、"アードレー家の「直系」の男子"とある。「直系」となる
と、アルバートさんだけが持っていることになる)
-
エルロイ大おばさまのセリフ
「ウィリアム大おじさまのきめたことは絶対です・・・したがわなければなりません・・・」
「あなたもアードレー家の一員になったのです。これからは行儀作法をしっかりまなんで家名をはずかしめないよう りっぱなレディーになるよう心がけなさい」
- きつね狩り
きつね狩りなど一族の集まりがある
「親族の人って何人くらいきてるの?」 「100人以上お集まりです」
「すごい人。あれが全部アードレー家の一族」
「アードレー家の正装がよくにあうじゃない」
- スコットランドに別荘がある
- キャンディがシカゴの摩天楼を案内されたとき
キャンディ 「ねぇ あそこにアードレー家の紋章が!」「あったちにも!」
アニー 「アードレー家のもってる銀行とか工場がこの街にはたくさんあるのよ」
- ストラトフォード劇団のシカゴ公演
イライザ 「慈善公演っていうのは一般のひとたちは見られないのよ。」「招待客とそのまちの名士だけがいけるのよ」
アーチー 「このシカゴでアードレー家を招待しないでだれを招待するんだ」
ステア 「アードレー一族にはいちばんいい席が用意されてあるって!」
(※一番いい席ということは、アードレー家はシカゴで一番の名士ということになる。アメリカ全体ではどれくらいのレベルの設定だったのだろう?)
- ニールとの婚約パーティーでアードレー家のだれかのセリフ
「めずらしいな アードレー家の一族がこんなにあつまるなんて・・・」
(※きつね狩りはやらなくなっただろうから、それ以来の集まり?)
- 先代のウィリアム・C・アードレー氏はフランスへ行ったとき、孤児のジョルジュを拾いアメリカへ連れて帰った。
(※たいせつな書類を持っていたとあるので、普通に考えると仕事で渡仏。先代の時代には、すでに事業でフランスに進出していた? それともフランスに別荘を買いに?)
- 一族の長は大総長と呼ばれる。
- アルバートさんは幼くしてアードレー家の大総長を継いだ。
- アードレー家のパーティーでは、子供たちが民族衣装を着てバグパイプをふき、おどるとある。
- アルバートさんが子供のころはエルロイ大おば様とアードレー家の長老たちがしきっていた。
- 「イギリスに進出していた仕事も、どうにかうまくいきはじめたんでね。」
- 「遊びにきたわけじゃないんだよ。サンパウロは暑くて、...」
- レイクウッドのメモリアル・ルーム
たくさんのアードレー家の人々の肖像画がある。アンソニー、ステア、ローズマリー・ブラウン。アルバートさんの母親。 - 子供のころに疲労が原因で他界。柱のウィリアム・C・アードレー
- そのころ、アードレー家は銀行をはじめ、かなり手広く事業をやっていた
- アードレー家は格式と名誉を重んじる
- 大総長はぜったいにアードレー家の直系「ウィリアム」でなければならない
-
先祖についてのアルバートさんのセリフ
「だいたい先祖のウィリアム・アードレーなんてスコットランドのいなかものだったんだよ。それが大総長だの家がらだのいうようになったなんておどろきだが、...」 - ローズマリーとブラウン氏の結婚
「ブラウン氏は生まれは悪くないがただの船長」と大騒動になった。
これ以上のことは、原作者の頭の中にしかありませんが、
・アードレー家はスコットランドではどんな家柄だったのか
・初代ウィリアム・アードレー氏は、いつ何のために新大陸アメリカに渡ったのか
・アメリカではなぜ銀行業をはじめたのか
 スコットランドの特徴
スコットランドの特徴
イギリス (the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)は4つの地域・民族から構成されており、地方行政制度も各地域によって異なっています。・イングランド (首都: ロンドン)
・スコットランド (首都: エディンバラ)
・ウェールズ (首都: カーディフ)
・北アイルランド (首都: ベルファスト)
スコットランドは、1707年の合同法によってイングランドに併合されるまで独立した王国でした。 300年たった今でも、敵対関係にあったイングランドへの対抗心・独立心は旺盛なようです。
<スコットランド人気質>
「ケチ」で「頑固」。
スコッチという言葉は世界ではケチの代名詞。
スコットランド・ジョークにはケチ話が多い。開き直り方は関西人に類似しているらしい。
キャンディの作品の中で、最もスコットランド人気質を発揮しているのがエルロイ大おば様かもしれません。
ケチかどうかは知りませんが、エルロイ大おば様の頑固さは相当なもの。
そして古い秩序、誇りや伝統を重んじていて、血族を大切にしています。
「ウィリアム大おじさまのきめたことは絶対です・・・したがわなければなりません・・・」のセリフが象徴的なのですが、一族の長の言うことを絶対とし、厳格に守り通すのもスコットランド氏族制度の特徴の一つ。
アメリカに入植して何代も経てば、昔の伝統やしきたりといったものはだんだん薄れていくように思うのですが、その逆になる場合もあるのかも。
19世紀頃、スコットランド系の子孫が自分の祖先の氏族をたどれるような名簿が出版されていたそうです。 『タータンチェックの文化史』によると、この名簿の本の影響でカナダではタータン人気が過熱。スコットランド系の子孫になりたがり、タータンを着用できることがひとつのステータス・シンボルとなったとある。
自分の祖先の歴史やタータンなどルーツがわかるとなると、祖先の母国への思いはますます強くなっていきますね。
<地理>
スコットランドは北部のハイランド(高地地方)、南部のローランド(低地地方)に分けられる。
スコットランドの一番高い山のベン・ネヴィスは標高1343メートルで、その他の山のほとんどが1000メートル以下。高地地方とはいってもそれほど高くはないようです。
文章だけではピンとこないのですが、スコットランドの風景は、映画『ハリー・ポッター』シリーズで見ることができます。
「なかよしまんが新聞」にあるグランチェスター家の別荘の位置は、ハイランドとローランドのちょうど境目あたり。そういえばアードレー家の別荘も近くでしたね。
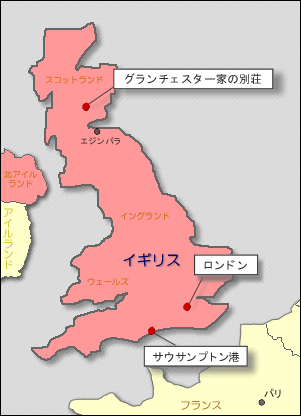
山や湖水も近くにあり、マンガの風景を見る限りハイランド地方という印象をうけます。
スコットランドにグランチェスター家の別荘に似ている城はないか探してみました。
建物の感じと古さ加減では、ホリルードハウス宮殿が似ているようです。(この古い感じがグランチェスター家は中世から続く格式ある家柄のような印象をうけます)
インヴァレリー城は全体的な雰囲気が近いかと思います。小説のグランチェスター家のように庭園は荒れはててはいませんが、木立にかこまれて、近くに湖や小川が流れており、古さも同じくらいかと。15世紀から続くアーガイル侯爵一族が今でも住んでいるそうです。
湖畔の近くに聖ポール学院の生徒たちが宿泊できるような教会、グランチェスター家やアードレー家の別荘があるサマースクールの村は、きっと有名な避暑地という設定なのでしょう。
<気候>
夏と冬が長い。
真冬は9時頃明るくなり、午後3時過ぎには暗くなります。
6月から9月までの夏は(夏というよりすごしやすい春か秋)、午前3時過ぎに日の出となり、午後11時頃にやっと暗くなります。
9月はスコットランドで一番快適な天候が続くベストシーズン。
10月に入るとスコッチ・ミストと呼ばれる霧が多く発生する季節になります。そして観光はシーズン・オフに。
スコットランドは日本の北海道よりも北に位置するため、冬はものすごく寒いという印象がありますが、カリブ海の暖流のおかげでほとんど零下にはならないようです。
マンガでは、スコットランドのグランチェスター家の別荘で暖炉をたいています。(小説ではサマースクールに着いた翌日の7月23日のこと)
夏に暖炉か?と思いますが、スコットランドの7月の最低気温(月平均)はエディンバラで11度くらい(最高気温は18度)。ハイランド地方だともう少し寒くて8度くらいです。
テリィも言っていましたが、夏とはいっても湖の水もかなり冷たい。ボートから湖に飛び込むなんてイライザも無茶しますね。
 スコットランドの文化
スコットランドの文化
<クラン (氏族)>ハイランド(高地地方)では伝統的な「クラン」と呼ばれる氏族社会がありました。
クラン(氏族)とは、クラン・チーフをリーダーとする小さな独立国家のようなグループ。
のちにローランド(低地地方)にも広がる。(クランは約300あるそうです。)
アードレー家がスコットランドではどの程度の家柄だったのかは、マンガや小説ではわかりませんが、このクラン(氏族)に関連することがらは、アードレー家のしきたりや伝統を理解するヒントとなりそうです。(ちょっとおおげさかな?)
下記リンクを見るとクランは想像していたより規模が大きい。
法律の範囲内ですが、ある程度自治が認められており、日本でいう藩のようなもの、クランチーフは殿様みたいなものと書いてある本がありました。
[クランの構成要素]
- クラン・チーフ − clan chief
クランのリーダー(氏族長) ※アードレー家でいえば大総長
- チーフテン − chieftain
クラン・チーフの息子(直系)/分家の長
※どちらが正しいのか不明。文献により異なる
- タックスマン(地主) − tacksman
クラン・チーフが地主(ジェントリ)の場合もある。
- クランメンバー − clansman(クランズマン)
チーフと同じ姓を持っている者。血族、またはチーフに忠誠を誓った者。
農民なのだが、戦闘時には兵士となる。
血族でなくとも、チーフと同じ姓名を名乗っていた者もいる。
チーフには地代を払う。
姓名が違うクランメンバーはSEPT(セプト)という。
クランメンバーは血縁の親族だけではなく、忠誠を誓った人もクランに属すことができた。
クラン・チーフは金銭ではなくクランの人数を重要視していた。戦争の時などチーフの権威が示された。
現在、クラン制度は廃止されています。
【クランの社会的・経済的な制度】
- 結婚
結婚は、クラン間の関係・絆を強くするために重要な意味を持っており、商業的な契約でもあった。
アードレー家での結婚を見てみると、
[エルロイ大おば様]
小説には恋愛結婚とある。(意外だ)
若い頃を思い出せとキャンディに手紙に書かれる。(そのあとアーチーとアニー
は婚約できたのでこれがきいたのか?)
先代のウィリアム氏がなくなったあと、「大総長」の代理のようなことをやってき
たわけだから、一族を守っていかなくてはという重圧は相当なものだったに違
いない。そのころ長老たちはまだ生きていたとはいえ、30代(予想)でしかも
女性でその役割をこなさなければならないなんて...
と、いろいろ想像が膨らみます。
[アンソニーの母ローズマリー]
小説によると、生まれは悪くないが船長というブラウン氏との結婚は大騒動と
なった。エルロイ大おば様は大激怒。その後、かけおちして結婚。
そしてそのかけおちにはジョルジュが一役かっていた。
結局にところ、本人の強い意志と有能な協力者が必要ということらしい。
[ラガン夫妻]
詳しいことは何も書いていないのですが、ラガン家がスコットランド系とあった
ので、一族間での結婚のような気がします。
でも、基本は政略結婚なんでしょうね。
- 傅(めのと)制度
クラン・チーフの子供が地主や他のクランのチーフに養育されることをいうらしい。
そうして、預けられた家と硬い絆を作っていくというもの。
- 忠誠
弱いクランが、強いクランの傘下に入ること。
守ってもらうかわりに土地の地代などを払うことになる。
- マクドナルド (MacDonald)
クランの中で最大。多くの分家・分派がいる。
- キャンベル (Campbell)
マクドナルド一族と対立している有力クラン。こちらも分家が多い。
・Campbell of Argyll (本家)
・Campbell of Loudoun (分家)
・Campbell of Breadalbane (分家)
・Campbell of Cawdor (分家)
上述のインヴァレリー城のアーガイル公爵は、このキャンベルのクラン・チーフ。
アメリカやカナダに移民したのクランメンバーたちのサイト
・結婚などで苗字がかわっても自分が一族に属するかどうか調べられる。(SEPT)
・子供用のページがわかりやすい
<名前>
【先祖代々同じ名前】
格式と名誉を重んじるアードレー家では、大総長はぜったいにアードレー家の直系、「ウィリアム」でなければならなかったんだ。
と、小説でアルバートさんが言っています。
アルバートさんの名前は「ウィリアム・A・アードレー」。お父さんは「ウィリアム・C・アードレー」。 きっとその前も「ウィリアム...
スコットランドのクラン「キャンベル家」を見てみると、2、3、5〜10代目とみんな「アーチボルド・キャンベル」。途中で名前がかわっている時もありますが、何らかの理由で弟が継いでいるようです。でも必ず子供には親と同じ名前をつけている。
理由はわかりませんが特にイギリスは多いようですね。
【名前でスコットランド系かがわかる】
スコットランド系では「マック(Mac)」がつく姓が多い。(Macはもともと息子の意)
・マクレガー(MacGregor)
キャンディに出てきたマクレガーさんも、スコットランド系だったのですね。
・マッカーサー (MacArthur)
・マッカートニー (Macartney)
・マッキントッシュ (Macintosh)
・マクベス(MacBethad)
イギリスの産業革命期には、スコットランド人の優秀な技術者や発明家がたくさん登場しました。歴史的にも有名な人が多数います。
『スコットランド歴史を歩く』によると、"どんな蒸気船に乗っても、機関室で 「ヘイ、マック!」と呼べば必ず答えが返ってくるといわれた" とある。
(技術者 = スコットランド人 = マック○○ が一般的だったらしい。 )
<キルト>
スコットランドの民族衣装。
キルトとは、ハイランド出身の男性が身に付けるハイランド・ドレスの一部のこと。
じゃあアードレー家はハイランド出身ということになるのかと思いましたが、200年ほど前からスコットランドを象徴するものになり、ハイランド出身ではない人でもキルトをはくようになっていました。
<タータン>
クラン(氏族)ごとにタータン(格子縞)があります。
日本の家紋と同じで、身に付けているタータンでその人の家がわかるようになっています。
タータンにはいくつかの種類があります。 (※下記はタータンの例。他にもあります)
|
タータンのデザインや柄には名前がついており、正装用タータンは「ドレス・アードレー」、キャンディが着ていた狩猟用タータンの場合は「ハンティング・アードレー」となる。
クラン(氏族)ごとに決まっているとはいうものの、法律的には他のクランのタータンを着てはいけないという規定はなく、私たちも好きな柄のタータンを身に付けることは可能らしい。
スコットランドのタータンのお店には、クランの名前のついているタータンが売っています。アードレー家のタータンがあったら欲しいですね。
王室が用いる「ロイヤル・タータン」、軍服の「アーム・タータン」、「警察隊用タータン」など着てはいけないタータンというものがあり注意が必要です。
<バグパイプ>
祭りや結婚式などあらゆるイベントに欠くことのできない伝統的な民族楽器。
行進曲『スコットランド・ザ・ブレイブ』という曲が有名。たしかアニメで使われてた記憶が。
スコットランドのおみやげ屋さんで、この曲が使われている商品には、日本語で「キャンディ・キャンディ」と書いてある紙が貼ってあるのをよく見かけました。わかりやすい。
美しい音色を出すには相当練習しなければならず、肺活量よりも空気を勢いよく吹き込むための鍛えられた腹筋が必要。
このバグパイプの音色について、キャンディは『かたつむりがたくさんはってるみたいな音ね』と素直な感想を述べていますが、 戦争のときには「士気高揚」と「敵を威嚇」する武器となりました。(日本でいう法螺貝みたいなもの?)
スコットランドの軍隊といえば、ハイランド連隊。
特に「ブラック・ウォッチ」− 黒い見張り番 − というおそろしく強そうな名前の精鋭部隊が有名で、やはりおそろしく強かったらしい。(バグパイプ演奏者が随行する)
ワーテルローの戦いでナポレオンに勝利したウェリントン将軍は、スコットランド人の兵隊を率いて戦場に赴いた時のことを、『私自身が非常な恐怖を感じた』と、味方をも怯えさせていたバグパイプのその異様な響きをこのように言い表しています。
でも、丘の上の王子様がキャンディに聞かせた音色は、妙な音ではあるけれど、きっと王子様らしいやさしい音色だったのでしょう。
<紋章・バッジ>
スコットランドの紋章は、厳格なルールがあり、紋章院長官が管理し長官の許可なくして勝手に紋章を帯びることは許されません。
(ただし、海外に住んでいても祖先がスコットランド人であれば紋章は与えられた)
図柄から家系相互の親疎関係がわかるようになっており、人生訓のようなモットーが付されています。
各クラン(氏族)の紋章・バッジ・植物・タータン・モットー・歴史・地図
上記のリンクには残念ながらアードレー家のものはありませんが、もしあったとしたらどんな内容になるか真似して作ってみようか、なんて考えてしまいました。各クランの紋章を見てみましたが、マンガのアードレー家の紋章が一番かっこいいですね。あの「わしの紋章」にはどんな意味が込められているのでしょうか。
あと上記リンクにもありますが、紋章の「バッジ」もスコットランドのクラン(氏族)ではタータン同様、重要なものの一つです。(帽子につけていたようです。あと軍隊で使用)
The Court of the Lord Lyon (スコットランド紋章院)
Scottish crest badge (スコットランドの紋章のバッジ - wikipedia)
マンガでは「アードレー家の(直系)の男子がもつ」というバッジ。
直系で大総長であるアルバートさんだけが持っていましたが、このしきたりは、祖先のスコットランドの伝統を踏襲したものかもしれません。
【マンガや小説に出てきた紋章・バッジ】
- 丘の上の王子様が落としたわしの形の銀バッジ(鈴がついている)
- レイクウッドのアードレー家のバラの門
- レイクウッドのアードレー家の石の門
- レイクウッドのアードレー家の水の門
- ジョルジュがポニーに家に乗ってきた車のドア
- スコットランドの別荘の門
- シカゴのアードレー家の銀行の正面玄関
- シカゴのアパートでキャンディが見つけたアルバートさんのアードレー家のバッジ
(コミックスではカットされたシーン)
【鉄鋼王カーネギーの紋章】

スコットランド出身の鉄鋼王カーネギーが、故郷に図書館を寄贈したときの紋章の話がありました。
建物の設計技師に「紋章を掘り込みましょう」と言われたのですが、手織り職人だったカーネギー家がそんなものを持っているわけがなかったので「ドアに太陽を彫って、光はここより発するとでも刻むんだな」と言ってカーネギーはカラカラ笑っていたそうです。
なんかその場の思いつきで適当に決めた感じですね(笑)
参考文献 『独占者の福音 (大森実 著)』
<ハイランド・ゲームズ>
スコットランドの各地で毎年5月から9月にかけて行われる伝統的なスポーツイベント。
バグバイプの演奏・ハイランドダンス・丸太投げ・ハンマー投げ・石投げその他の重量競技があります。
起源については諸説あり(11世紀からという説や1314年説など)、現在行われているハイランド・ゲームズは19世紀にはじめられたもの。
キャンディがサマースクールに行ったスコットランドの村のお祭りは、ハイランド・ゲームズではないかと思います。
マンガにはキルトを着たバグバイプ演奏の行列、ハイランドダンスなどの描写があります。(丸太投げはありませんでしたが)
<キツネ狩り>

【イギリスのキツネ狩り】
スポーツとして銃を用いず、猟犬を追いかけて獲物を仕留めるハンティング。
19世紀初頭のイギリスでは、「狩猟会は猟犬の持ち主が主催し、費用も一人でもつという社交界の一大行事」でした。 19世紀も後半になると、「貴族の懐具合も悪くなり、会費制の狩猟会が普通」になっていったそうです。
猟犬は52匹で一組となり、狩猟期にそなえてふだんから特別な訓練を受けさせている。
イギリス(イングランドとウェールズのみ)で2005年2月からキツネ狩り禁止法が施行されました。スコットランドではキツネ狩りに適する平坦な土地が少ないので、今はほとんど行われていないそうです。
参考文献 『スコットランド文化事典』、『十九世紀イギリスの日常生活』
【アメリカのキツネ狩り】
キツネ狩り用の犬では、アメリカ原産の最上犬種に「アメリカン・フォックスハウンド」というイングリッシュ・フォックスハウンドを掛け合わせた猟犬が有名。
(スピードとスタミナを兼ね備えた、キツネ狩りのためだけに作られた犬)
アメリカでキツネ狩りとはどのようなものだったのでしょうか?
18〜20世紀初頭のキャンディ時代くらいまでは、キツネ狩りはアメリカの上流階級の娯楽だったようです。
『モルガン家 (ロン・チャーナウ 著)』によると、その後の1920年代のアメリカの繁栄期(キャンディの最終回より数年後)は、「ウォール街の株仲買人たちが英国伝統の大地主を夢みて、ポロ用の馬を飼育しキツネ狩りに興じた」とある。
上流階級の娯楽というより、金持ちのステータスを追い求める人たちの一種のアイテム的なものになっていったように思います。
【アードレー家のキツネ狩り】
マンガの様子から、キツネ狩りはアードレー一族が一堂に集まる慣例のイベントとなっているようです。
スコットランドの氏族制度では、一族の召集(クラン・ギャザリング)というものをとても重要視しています。『タータンチェックの文化史』によると、「常に人々を引き付け、一族の帰属意識の強化が不可欠」とある。
アードレー家もそうやって血族の結束を強めていったのでしょう。
(でも、アルバートさんの代から一族の集まりは減っていきそう)
<宗教>
スコットランドの守護聖人は聖アンデレ。
十字架は「+」ではなく「×」の斜め十字(セント・アンドリュー・クロス)。
教会はプロテスタントの「チャーチ・オブ・スコットランド (スコットランド国教会)」で、イングランドの「チャーチ・オブ・イングランド (イングランド国教会)」のプロテスタントとは異なり、長老派(聖書を絶対視する原理主義的な宗派)である。
偶像崇拝の排除によりプロテスタントに多発した「魔女狩り」が最も多く行われた。
国王や女王が教会を支配しているイングランドとは違い、民衆が自分たちで教会の指導者を選ぶなど草の根的なところが特徴だそうです。
マンガに教会のシーンが何度か出てきますが、アードレー家が長老派かどうかまではわかりません。
ただ、カトリックかプロテスタントかとなると、プロテスタントにはイエスやマリア像はなく、十字架しかないので、単純にそこだけで見ていくと下記のようになります。
- ポニーの家は、マリア様の絵がかざってあり、キャンディがもらったクロスにはマリア像がついているのでカトリック。
- ロンドンの聖ポール学院は王立だったのでプロテスタント (イングランド国教会)。
- ステアのお葬式の時、キャンディが入った礼拝堂はマリア像がなく十字架しかないので、アードレー家はプロテスタント。
<ショートブレッド>
スコットランドの伝統的なお菓子。バターたっぷりでサクサクした厚焼きビスケット。
日本ではスーパーなどで赤いタータンチェックのパッケージ「Walkers (1898年)」をよく見かけます。
マンガにはキャンディがスコットランドのサマースクールから帰ってきたあと、買ってきたクッキーのおみやげをアニーやパティたちに「あとでたべましょう」と出しているシーンがあります。あのクッキーはもしかしたらショートブレッドかも。
<マクベス − シェイクスピアの戯曲>
スコットランド王のマクベス(1005-1057)は、シェイクスピアの四大悲劇の一つ『マクベス』のモデル。
劇中の話とは違い、実際のマクベスは統率力のある賢王だったそうです。
この戯曲の舞台とされる「コーダー城」と、マクベスがダンカン王を殺したとされる部屋がある「グラムズ城」は実在の城。
ただし、どちらの城の話もシェイクスピアの創作で、史実とは違う。
テリィはスコットランドで、シェイクスピアの戯曲集を読んでいました。
黒い線や書き込みがいっぱいあったという戯曲はどの作品だったのでしょうね?
<ブリタニカ大百科事典 (1768) >
現在も刊行が継続されている英語で書かれた百科事典の中で最も古く最大のもの。
出版はスコットランド啓蒙の黄金時代のエディンバラ。
当時のほかの百科事典との違いは、「実用性」重視で、知識が簡単明瞭に伝えられるようにしたこと。 アルファベット順のリファレンスではなく、主要テーマを設けて論文形式で説明する方式をとった。 一般市民を対象とし、ほかの百科事典のように限られた知識階層のために作られたものではない。
<ネッシー>
「ネス湖の怪獣ネッシー」の一番最初の目撃情報は、1930年の新聞記事。
1934年にウィルソンが撮影した写真が一番有名ですが、あの写真のネッシーはおもちゃの模型を使った偽者だったらしい。
<スコッチ・ウィスキー>
スコットランドで作られたウィスキー。
糖化・発酵・蒸留・熟成までの製法は、法律で定義されている。
<リプトン>
紅茶で有名なリプトン。
サー・トーマス・リプトンはスコットランド生まれ(1850-1931)。
ニューヨークで資金と小売技術を身に付け、グラスゴーに戻り食料品店を開く。30才ですでに百万長者となっていた。
慈善事業にも力を注ぎ、1898年にナイトの称号を与えられた。
<アーサー・コナン・ドイル (1859-1930)>
『名探偵シャーロック・ホームズ』の作者。
エディンバラの政治風刺漫画家の末っ子に生まれた。エディンバラ大学の医学部を卒業し開業医となる。北極海の捕鯨船や西アフリカへの商船の医者として働きながら文筆活動を始めた。1887年にシャーロック・ホームズシリーズの最初の作品『緋色の研究』を発表。
<スティーブンソン>
『ジギル博士とハイド氏』、『宝島』の作者。エディンバラ生まれ。
蒸気機関車で有名なジョージ・スチーブンソンは彼の叔父。
<その他>
・女王メアリ・ステュアート − スコットランド史では最大のヒロイン。
・ジェームズ・バリ − 『ピーターパン』の作者。
・ウォルター・スコット − 歴史小説家。
− 現在のスコットランド紙幣に肖像が印刷されている。
・ロバート・バーンズ − 詩人。日本でも有名な「蛍の光」の原詩はバーンズ。
・探検家リヴィングストン − アフリカ各地を探検。
・探検家マッケンジー − 北米大陸横断と北極海への川系の発見。
・アダム・スミス − 『国富論』を執筆。
・ツイード(毛織物) − 1892年にツイード織を発明。
19世紀のヨーロッパ社交界の高級織物として定着。
・ベイ・シティ・ローラーズ
− 日本でタータンチェックを広めたのはベイ・シティ・ローラーズ?
ちょうどキャンディと同時期にブームでした。
・俳優 「ショーン・コネリー」
− スコットランド出身。
ナイトの称号を与えられた。授与式ではキルトの正装で現れたことでも有名。
・映画 『ブレイブ・ハート』
− スコットランドの独立のために戦ったウィリアム・ウォレス(実在)の生涯を描く。
ただし、ロケ地はスコットランドではなくアイルランド。
・映画 『ロブ・ロイ』
− 18世紀スコットランドの実在の英雄ロブ・ロイを描いた映画。
ロケ地はスコットランド。本物のハイランドの自然が見れます。(ロケ地詳細)
・映画 『ハリー・ポッター』シリーズ
− 物語の世界はスコットランドが舞台といわれているらしい。
魔法なのでケルト神話ということなのでしょうか?
『ハリー・ポッターと賢者の石』 (スコッドランドでのロケ地詳細)
『ハリー・ポッターと秘密の部屋』 (スコッドランドでのロケ地詳細)
『ハリー・ポッターとアズカバンの囚人』 (スコッドランドでのロケ地詳細)
『ハリー・ポッターと炎のゴブレット』 (スコッドランドでのロケ地詳細)
 あまり知られていないスコットランド
あまり知られていないスコットランド
<教育制度>イギリス教育制度の歴史といえば、イングランドのオックスフォード・ケンブリッジやパブリックスクールといった派手めなほうばかり注目されがちですが、スコットランドの教育制度はすごかったのです。
スコットランドの教育の特徴は「実学主義」。(産業に直結する学問)
産業革命期に多数の科学者・発明家・実業家を輩出しています。
その実学主義を生かした銀行・会計学などがスコットランドで発展し世界に広まりました。
【教育の機会】
スコットランドは1496年にヨーロッパ最初の義務教育法を確立。(1教区に1学校の設立を促す法令)
貧富の差にかかわらない能力主義による教育機会が与えられており、経済的には貧しい国であったが、教育水準は高かった。それには教会の役割が大きかった。
(18世紀には、素質さえあればどんな生まれでも教区や地主が助けて、必ず大学まで行けるというシステムが出来上がっていた)
このあたりが、貴族や地主のみ受けられたイングランドの教育制度と大きく違うところ。
ただし、いいことばかりではなく、奨学金が足りなくなったり、イングランドとは違いスコットランドは「通学制」だったので、ハイランド地方など1教区が広い地域では、遠くて学校に通えないなどの問題もあったようです。
【イングランドとの比較】
|
参考文献 『イギリス教育史』、『近代スコットランド社会経済史研究』
【大学】
16世紀にイングランドにはオックスフォードとケンブリッジの2大学しかなかったのだが、スコットランドには下記4大学があり、教育・大学においては先進国であった。
・セント・アンドリューズ大学(1411) − 世界に先んじて教授制を取り入れた
・アバディーン大学(1450) − 世界で最初に医学部を設置
・グラスゴー大学(1494) − 『国富論』のアダム・スミス
・エディンバラ大学(1582)
では、何がどう進んでいたのか? 当時のヨーロッパの大学の中で時代の最先端って何なのか? どうもすっきりしなかったので具体例を探してみました。(一番わかりやすかった例が下記です)
・「ニュートンの理論(万有引力)」がいち早く講義に取り入れられていた。
・「コペルニクスの天文学」も、宇宙論講義の基礎として取り上げられていた。
18世紀は医学、自然科学、数学の分野では競争相手が皆無に近いとあり、特にエディンバラ大学は称賛されている。
それとは逆に17世紀〜18世紀頃、スコットランドの大学に比べてイングランドの大学は評判があまり良くなかったため、家庭教師をつけて私教育を施す貴族・地主(ジェントリ)が多かった。(ちょっと意外な感じがします)
D・デフォー(1661-1731)『イギリス紳士大鑑』によると、「貴族約30,000家庭のうち長男を大学へ行かせているものは200家庭」とある。
昔のこととはいえ、地主を合わせたとしても30,000家庭もあったのか?とちょっと疑問なので調べてみました。
18世紀ものは見つからなかったので、19世紀 (1814年) の資料です。
|
参考文献 『十九世紀イギリスの日常生活』 1814年のイギリス社会一覧表より
19世紀初頭では地主階級合わせて約47,000世帯。けっこうな数ですね。
※現在は世襲貴族の数は約900家で、一代貴族が約340くらいだそうです。
18世紀中には、イングランドや北アイルランドからの学生が流入してくるようになります。
(当時イングランドには宗教審査があり、非国教徒は大学に入学できなかった)
そして、スコットランドの大学はイングランドのロンドン大学設立(19世紀)に大きな影響を与えた。
このような教育環境で育ったものの、就業の機会は少なく、国内では才能・技術を発揮することができませんでした。
しかし、19世紀、アメリカなど移民先でその技術・才能を開花させることになります。
そのため、優秀な人材が流出してしまい、スコットランドの教育・経済は衰退へと向かいます。
19世紀のヴィクトリア朝半ばには、エリート育成のイングランドのイートン校(パプリック・スクール)を模した私立の寄宿学校がスコットランドにも作られるようになります。
以前のように、「貴族も召使の子も肩を並べて座り、優越感や劣等感などない雰囲気の中で一緒に学び交流できた」学校は遠ざかっていきました。
<スコットランド啓蒙>
イングランドの『英国辞典 (1755)』の項目の一つ「カラス麦 (oat)」の話が有名。
カラス麦について、辞書には、
「イングランドでは馬の食うもの、スコットランドでは人の食うもの」
とあり、それに対してスコットランド人のジェイムズ・ボスウェルは、
「だからイングランドでは名馬が育ち、スコットランドでは人材が育った」
とやり返した。
これは、ジョークでもスコットランド人の負けず嫌いを表したものでもなく、事実そのとおりのことでした。
参考文献 『スコットランド歴史を歩く』
【パリやイングランド啓蒙との違い】
- 単なる思想運動ではなく、実学・実業・実利の追求。
- [啓蒙」と「教会」が対立しない。
※通常、理性の啓発によって進歩・改善しようとする「啓蒙」は、それとは逆となる
キリスト教の「神の啓示や奇跡」を重んじる精神を批判することになってしまうた
め、「教会」との対立は避けられない。
- エディンバラにはパリのような「サロン」が存在しない。
パリやイングランドのような貴族や富豪という不労働階級の集まりではなく、専門職階級の人たちが中心。
話題も実践的なテーマが多く、パリのように現実とほど遠いことを論じているわけではなかった。
ちなみに、管理人は当サイトで「キャンディ・キャンディ啓蒙」の活動中。(何なんだそれは!? 笑)
<発明>
|
<銀行・金融家>
銀行史・金融史を調べていたら、スコットランドがたまにでてきます。
スコットランドで有名なのは、バグパイブ・キルト・ネッシーなど上述した文化で、金融というのがちょっと以外な感じがしたので、スコットランドの金融史も調べてみました。
アードレー家の事業をなぜ銀行業にしたかは原作者のみ知る状態。
特に深い意味はなかったのかもしれませんが、アードレー家と祖先のスコットランドが「銀行」というキーワードでつながったので、たんなる偶然でもちょっと楽しい。
【現代の銀行業システム】
金融業でも両替商や金貸しはもっと以前からどこの国にも存在します。(有名なところではメディチ家の銀行とか)
現代に通じるシステムの基礎はスコットランド人が作ったものです。
下記にあげるものはスコットランド銀行業が考案したシステムです。スコットランドの倹約精神が生み出したといえる。
・株式会社制度
・支店制度
・定期預金
・投資信託 etc...(他にもあるのですが専門的になるので割愛します)
【イングランド銀行】
かつては「世界の銀行」といわれた大英帝国イギリスの中央銀行。(中央銀行は銀行の銀行。日本では日本銀行。アメリカではFRB)
そしてそのイングランド銀行は、1694年にスコットランド人の金融家ウィリアム・パターソンによって創設された。
彼は翌年の1695年にスコットランド銀行の創設にもかかわっている。
この時代すでにスコットランド人の多くの金融家が活躍しています。
【スコットランド銀行】
1695年にイングランド人ジョン・ホランドによって創設。
なぜイングランド人が創設? と思ったのですが、ジョン・ホランドはイングランド銀行を創設したウィリアム・パターソンの友人で、スコットランドで毛織物業を営んでいた商人。スコットランドの経済事情に精通していた。
このスコットランド銀行はイングランド銀行に対抗して創設された。
イングランド銀行は国に(イングランドの利益・独占のため)コントロールされていたが、スコットランド銀行はスコットランドの銀行・金融業の中心的役割を担っていた。
【日本銀行とスコットランドの金融家】
スコットランド人のA. A. シャンドが日本銀行の創立に貢献。(詳細は後述)
【スコットランド紙幣】
昔からスコットランドでは、世界各国で通用する女王が印刷してある紙幣ではなく、ロイヤル・バンク・オブ・スコットランドやバンク・オブ・スコットランドなどの銀行が、それぞれ独自の紙幣を発行しています。(現在もイングランドでは使えない場合がある)
マンガでは、サマースクールに行く前にジョルジュがキャンディにお金を送っていますが、あのお金はスコットランド紙幣が入っていたかもしれません。(さすがに全部スコットランド紙幣だとキャンディも困るので、入っていたとしても一部だけ)
キャンディの時代は、現在のように観光地で気軽に両替できたわけではありません。
スコットランド紙幣への両替は聖ポール学院が代行してくれるのかもしれません。でも、ジョルジュだったらそこまで気を利かせているような気がします。
アードレー家の事業は銀行業。ジョルジュがスコットランド紙幣のことを知らないはずはない。
 アメリカとスコットランド
アメリカとスコットランド
<アメリカへの移民>スコットランド人の移民先はカナダ・アメリカ・オーストラリア・ニュージーランド・インドなどですが、移民先で最も成功したのがアメリカです。
その新天地アメリカでのスコットランド人の活躍は群を抜いていました。
それは彼らの母国での高い教育水準が反映された結果です。
初代ウィリアム・アードレー氏はいつ、アメリカへ移民したのでしょうか?
【スコットランド人のアメリカへの移民】 (移民のはじまり〜キャンディが生まれる年まで)
|
参考文献 『近代スコッドランド移民史研究 御茶の水書房』
スコットランド人移民は、多くの政治家・思想家・発明家・技師・企業家を輩出しました。
そして銀行・金融・保険・鉄道などのビジネスにおいてもアメリカ社会の形成に大きな貢献をすることとなります。
<カーネギー (1835-1919)>
スコットランドの古都ダンファームリンからアメリカに移民。
13才でピッツバーグの綿工場の「糸繰り子」として就職。 24才でペンシルバニア鉄道の工事監督となり、「鉄道の都」スコットランドのスプリングバーンからの技術移転を見越して、鉄道需要用の鉄鋼工場を建設。「アメリカ鉄道建設ブーム」に乗り、30才になる前に大富豪となり「鋼鉄王」と呼ばれるようになった。
引退後は慈善事業を行い、世界各地に2500もの図書館を寄贈し、大学・研究所へ援助も行った。奨学金に関する教育制度にも影響を与えた。今では一般的な奨学金制度は「スコットランド教育制度」から生まれたものだそうです。
<スコットランドにあるアメリカの大富豪の別荘>

アードレー家はスコットランドに別荘を持っていましたが、史実では約100年前のキャンディ時代に、アメリカの成金がスコットランドの城や別荘を買うことはできたのでしょうか?
イギリスの貴族階級では、次第に力をつけてきた成金のヤンキーを嫌い警戒していた時代です。
とりあえず、管理人が見つけたのは今のところ下記2名。
【カーネギー】
鉄鋼王カーネギーは19世紀末 (1898年?) に「スキボ城」を購入。
スキボ城は12世紀に築城。近くにマクベスの城もあり、付近一帯はシェイクスピアの舞台。
カーネギーはその城の農園に、数百人の農夫も雇っていたらしい。
【J.P.モルガン二世】
英国カントリーハウス好きの金融王モルガンの息子(J.P.モルガン二世) は、スコットランド東部の高原地方にあるガノッチーという狩猟用別荘を友人の投資銀行家と共同で購入。
「ヒースが一面に生え、深い峡谷が縦横に走り、サケの遡る小川が流れる夢のようなところ」とある。毎年8月には銀行家や貴族を招き、遊猟会を開いていました。(のちに英国国王ジョージ六世も加わったそうです。)
スコットランド出身のカーネギーはアメリカでの成功後に、図書館寄贈や教会への寄付などスコットランドへかなり貢献していて、故郷に帰れば凱旋将軍のように歓迎されていました。モルガンは当時アメリカ人実業家たちが不可能であった英国社交界に受け入れられています。懐事情が厳しい売主の貴族としては、どちらも喜んで売却できる相手だったのかもしれません。
アードレー家もスコットランド出身なので、成功者として扱いは良かったかもしれません。
カーネギーのような寄付に関してはどうなんでしょう? 聖ポール学院に対して行なっていたのは、「キャンディの特別室」と「シスターグレーのエルロイ大おば様への態度」で露骨にわかります(笑) 必要なところへの寄付は、金に糸目をつけないのは確かなようです。
 カナダとスコットランド
カナダとスコットランド
<『赤毛のアン』はスコットランド系>『赤毛のアン』の作者モンゴメリ (1874-1942 カナダ)の両親はスコットランド出身の移民。
そして旦那さんもスコットランド系で、スコットランドの国教である長老派教会の牧師。
子供のころは、まったく気付きませんでしたが、『赤毛のアン』にはスコットランドにまつわるものがたくさん出てきます。
- マシューとマリラはスコットランド系の移民2世。
- マシュー・マリラ・アンの通っている教会は長老派。
- アンの生まれ故郷はスコットランド人が多く入植したノヴァスコシア州なので、アンはスコットランド系かもしれない。(ノヴァスコシアは新スコットランドという意味)
- 赤毛とそばかすはケルト系のスコットランド人やアイルランド人の特徴。
『ナショナルジオグラフィック 2007年9月号』によると、スコットランドの赤毛人口は13% (世界では2%) 。そしてスコットランド人の4割は赤毛の遺伝子をもつ。
- 物語の中の詩はスコットランド作家ウォルター・スコットや詩人ロバート・バーンズ
- スコットランドのお菓子「ショートブレッド」が出てくる。
『赤毛のアン』では、作中のなにげないちょっとした表現が、実は「聖書」や「シェイクスピア」・「イギリス文学」の引用やパロディだったりします。
参考文献
『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア』
それも普通に読んでいたらまず気付かない。こういう背景を知ってからもう一度読み直してみると、深い作品だなあとつくづく感じます。
以前、原作者の水木先生のサイトに、"『赤毛のアン』は「キャンディ」を書く上での「ふるさと」のような作品" とありました。
キャンディキャンディという作品の中には、読者にも気付かないような作者の赤毛のアンへの思いがいろいろとちりばめられているのだろうと思います。
そして、「スコットランド系」というアードレー家の設定が、作品に深み・厚みを出しているものの一つとなっているのだと感じました。
 日本とスコットランド
日本とスコットランド
日本とスコットランドが一番近かった明治時代。日本近代化はスコットランド抜きでは語れないようです。
『スコットランド歴史を歩く』によると、明治日本のお傭い外国人50%の約2,000人がイギリス人で、その相当な部分がスコットランド人だったとある。
日本で有名なもの、活躍したスコットランド人、貢献した事業等はここには書ききれないくらいたくさんありますが、いくつかピックアップしてみました。
<蛍の光 - スコットランドの民謡>
明治に文部省が編纂した小学唱歌にはスコットランドの民謡がたくさんあるようです。
その中でも一番有名なのが「蛍の光」。
スコットランド民謡の特徴は、ヨナ抜きというドレミの音階から「ファ」と「シ」の抜けている音階のものが多い。(日本の民謡や演歌もヨナ抜き)
<トーマス・グラバー − 日本近代化の基礎を築いた>
貿易商。起業家。
日本で初めて蒸気機関を走らせたり、炭鉱開発、「キリン麦酒」の前身である「ジャパン・ブルワリーカンパニー」の創立など、日本では初めての事業を次々と興した。
三菱グループの創業を助け、鹿鳴館の名誉書記としても活躍した。
それら数々の功績により、外国人で初めて、勲二等旭日重光章を授与された。
日本人の妻ツル夫人は、プッチーニの名作『蝶々夫人』のモデルといわれている。(実際にはオペラのストーリーのように裏切られて自殺などしていないし、グラバーはスコットランドには帰らずに、生涯を愛妻ツルとともに日本で過ごしています)
グラバー邸は長崎の観光名所の一つ。
<A. A. シャンド − 日本銀行の創始と銀行教育に貢献>
銀行家。
大蔵省顧問を務め、日本銀行の創始と近代銀行制度の確立に貢献した。
大蔵官僚や国立銀行員に銀行取り扱い業務や経営管理を教える。
日本最初の銀行簿記の教科書である 『銀行簿記精法 (Bank Accountancy, 1873)』 を著した。
勲二等瑞宝章を授与されている。
 新大陸アメリカへ渡った初代アードレー氏
新大陸アメリカへ渡った初代アードレー氏
− 小説の第3部のアルバートさんの手紙より −「だいたい先祖のウィリアム・アードレーなんてスコットランドのいなかものだったんだよ。それが大総長だの家がらだのいうようになったなんておどろきだが、...」
アルバートさんがすごくいいヒントをくれたので、これをもとに「初代ウィリアム・アードレー氏」を推測してみます。(※史実をベースにキャンディの設定を加え、なおかつ管理人の願望も入っています。)
<管理人の考える初代ウィリアム・アードレー氏>
初代から銀行業を営んでいたという前提です。
管理人の勝手な想像なので、原作のイメージを壊したくない方は無視してください。
【いつ新大陸アメリカに渡ったのか】
初代ウィリアム・アードレー氏がアメリカへ渡ったのはイギリス産業革命期、アメリカの独立戦争後の18世紀終わり頃。
キャンディの時代より100年くらい前で、エルロイ大おば様より2〜3代前。
事業家であり、軍人ではない(作品からは元軍人がいた家系という雰囲気は微塵もない)
他の成功者と同じく20代で起業。
ゴールドラッシュや石油を掘り当て一攫千金で大金をつかんだのではない。
(※スコットランド移民の数やモルガン・ロックフェラー・カーネギー等とあわせて1830年代頃の生まれとしたいところですが、そうなるとアルバートさんの祖父と長老たちが初代となってしまいあまり面白くない。アードレー一族がぞろぞろと移民よりも1人の若者が夢を抱いての方がいい。代々とか祖先という表現があうようにもう少し前の時代にしてみました。)
【スコットランドではどんな家柄だったか】
スコットランドではハイランド出身で、クラン・チーフの直系や地主(ジェントリ)などの家柄ではない。
スコットランドの教育制度のおかげで、都会のローランドで教育をうけることができ、優秀なので地主の援助または奨学金で大学まで行くことができた。(銀行業なので、たたき上げではない)
スコットランド啓蒙・産業革命期で、素質・才能はあるのだけれど、ハイランドでは仕事がない。 ローランドの都市またはイングランドで働く。
イングランドへ移民するものも多かったが、特権的な地位はイングランド人、実務はスコットランド人で、いくらがんばっても超えることはできない「階級社会」のイングランドへの移住には興味がない。
(※このあたりは当時の事情そのままです。)
【アメリカでなぜ銀行業をはじめたのか】
アメリカでは独立戦争(1775-1783)が終結となり、イギリス軍や関連の組織がどんどん撤退してくる。
アメリカの植民地当時は、本国イギリスが公認の銀行業を禁止しており、イングランド銀行が銀行業務を独占していた。 そのため、それまでアメリカの銀行はなかったが、1781年に設立が許可される。はじめの頃は、主要な港町で商人達によって設立されていた。
参考文献
『アメリカの銀行 −その発展の歴史−』
銀行・会計学の専門知識を持っており独立精神旺盛だったので、これはチャンスと銀行で数年修行後、アメリカへの移民を決意し、大きな夢とともに新天地へと向かう。【その他】
二代目以降から、一族が大きくなるのと比例して保守的になっていき、家柄・格式などにこだわるようになった。
スコットランドの別荘に選んだ土地が、もし昔住んでいた土地だったとしたら、グランチェスター家の祖先とアードレー家の祖先が出会っていたかもしれない。
(ちょっと考えすぎですね...きりがないので、もうこのへんで終わりにします)
以上、管理人はアードレー家のルーツを、「典型的なスコットランド移民の成功者」+「キャンディキャンディの設定」+「スコットランドの歴史」でまとめてみました。何か他に面白いものを思いついた方は、ぜひ管理人に教えてください。

原作者の水木先生がキャンディのその後はもう書かないのであれは、その前の話を書いてほしいですね。管理人の推測は無難な感じになってしまいましたが、水木先生なら、きっとまた読者をあっと言わせてくれるはず。
参考文献
『蘇格蘭土と日本・世界 北政巳 (近代文芸社)』
『近代スコットランド移民史研究 北政巳 (御茶の水書房)』
『スコットランド歴史を歩く 高橋哲雄 (岩波新書)』
『スコットランドXIの謎 東浦義雄 (大修館書店)』
『近代スコットランド社会経済史研究 北政巳 (同文館)』
『スコットランド文化事典 (原書房)』
『タータンチェックの文化史 著:奥田実紀 (白水社)』
『イギリス教育史 田口仁久 (文化書房博文社)』
『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア 集英社 松本侑子』
http://www.tartans.scotland.net/index.cfm.htm
http://www.scottishtartans.org/tartan.html
『アメリカの銀行 −その発展の歴史− 文雅堂銀行研究者』
『アメリカの銀行制度 日本経済新聞社』
『近代スコットランド移民史研究 北政巳 (御茶の水書房)』
『スコットランド歴史を歩く 高橋哲雄 (岩波新書)』
『スコットランドXIの謎 東浦義雄 (大修館書店)』
『近代スコットランド社会経済史研究 北政巳 (同文館)』
『スコットランド文化事典 (原書房)』
『タータンチェックの文化史 著:奥田実紀 (白水社)』
『イギリス教育史 田口仁久 (文化書房博文社)』
『赤毛のアンに隠されたシェイクスピア 集英社 松本侑子』
http://www.tartans.scotland.net/index.cfm.htm
http://www.scottishtartans.org/tartan.html
『アメリカの銀行 −その発展の歴史− 文雅堂銀行研究者』
『アメリカの銀行制度 日本経済新聞社』