
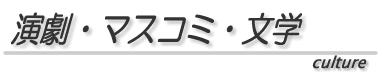
 演劇
演劇
<20世紀初頭のアメリカのショー・ビジネス>当時は、筋が簡単で主人公と悪役がはっきりした "正義が必ず勝つ" 系のメロドラマ・冒険・コメディなどの「大衆演劇」、気取らないで楽しく覚えやすい音楽の「ミュージカル・コメディー」、登場人物・設定・入場料が労働者向けにしてある「映画」(サイレント映画)などが流行しました。
参考文献 『アメリカの歴史4 アメリカ社会と第一次世界大戦』
<100年前のブロードウェイ>
19世紀末から20世紀初頭、ロンドンやヨーロッパの話題になった舞台が後からニューヨークで上演されるという現在とは「逆」の状況でした。
ブロードウェイではシェイクスピアなどの古典演劇が数多く上演されていました。
1915年には大劇場ではできないような実験劇を上演する「小劇場運動」が盛んになり、19世紀の大衆演劇は近代劇へ、娯楽から芸術へと進化し、アメリカ独自の演劇文化が発展していきます。 1920年代以降、ミュージカルで多くのヒット作品やヒット曲が生み出されました。
【舞台・映画・音楽の年表】
|
【演劇・ミュージカル・再演舞台統計表】
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
『ブロードウェイの魅力 丸善ライブラリー』 より抜粋
<テリィが演じた劇>
- ストラスフォード劇団
リチャードIII (役不明。新聞には「有望な新人あらわる!」という記事)
リア王 (フランス王役。シカゴで公演)
ロミオとジュリエット (ロミオ役。新聞には「ロミオとジュリエット不評!」の記事)
ハムレット (小説版のみ。第3部のその後の話)
- ロックスタウンの場末の劇場
胸さわぎ(空騒ぎのパロディか?)
新聞・雑誌にはテリィの演じた「ハムレット」が大評判という記事が掲載 されていたとか。
折りしもテリィがストラスフォード劇団に戻った1916年はシェイクスピア没後300年の年。
ブロードウェイではシェイクスピアブームでテリィ人気に拍車がかかったかも。
<舞台の事故で足を切断した女優 − サラ・ベルナール>

サラ・ベルナール(1844-1923)はフランスの女優ですが、ヨーロッパだけではなくアメリカでも絶大な人気を誇る大女優でした。アメリカには何度も公演に来ています。
【舞台のポスター】
アルフォンス・ミュシャが舞台のポスターを描いていたので、サラ・ベルナールは写真や肖像画よりもポスターの絵の方が有名かもしれません。
『椿姫』はサラ・ベルナールの当たり役で、ミュシャは舞台衣装も担当。
ミュシャが描いた『椿姫』や『ハムレット』のポスターはすごい素敵です。私だったらポスターを見ただけで舞台を見に行くのを決めてしまうかも。
(※『ハムレット』の舞台ではハムレット役。サラは男役もいくつか演じています)
キャンディでは、テリィの演じる『ロミオとジュリエット』の似てない写真っぽい絵のポスターがでてきます。
【1905年に舞台で事故】
リオ・デ・ジャネイロで『ラ・トスカ』のお別れ公演中、サン・タンジュ城から飛び降りて自殺する最後の場面で、舞台裏にマットが置いていなかったため、右膝を負傷。
【1915年に切断】
10年前の怪我が悪化し、右足を切断。
(※ちょうどスザナも同じ年に右足を切断)
サラは右足切断後数ヶ月で、映画出演や北部戦線の兵士を慰問するなどして、女優業を再開しました。
※サラは劇場も経営していた。
【1916年から1年半のアメリカ公演の様子】
『サラ・ベルナールの一生』によると、「足こそ不自由だったが、ひとたび、舞台に出れば、上半身を昔ながらに軽く動かし、時には、片足でまっすぐ立つことさえあって、その黄金の声とともに、蘇ったように生き生きした姿はたちまち、周囲に光彩を放った」とある。
ちょうどその時、ニューヨークに滞在していた日本人の小説家(成瀬 正一)がサラの舞台を見た印象を当時の文芸雑誌に書いています。
「サラの今回の興行に対して、批評家は老いたる名女優に厳正な批評をするのを遠慮したのか、申し合わせたように口をつぐんで語らなかった。だが、観客の拍手は非常なもので、カーテン・コールが十四回もつづき、最後の日などは見物が熱狂して、ラ・マルセイエーズを合唱した。そして何より不思議に見えたのは、サラが、ほとんど、奇跡といってもいいくらいに、若く見えたことである。七十三だというが、自分には四十ぐらいにしか見えなかった」
実際には足だけではなくからだも衰弱していたため、医者が常に同行していたらしいです。でも舞台ではそんな様子は微塵もない。彼女が苦難に直面したときに口を付いて出る言葉は「何が何でもやりぬいてみせる」でした。サラの女優魂にはすごいものを感じます。
【スザナのその後は?】
スザナは実力はあったのかもしれませんが、まだ駆け出しの若手女優。その後、女優として復帰したとしても、大女優でありカリスマ性もあるサラ・ベルナールのようにはいかないかもしれません。
足が不自由になっても舞台にたち続けたサラの姿を見た観客や前線の兵士たちは、彼女の強い生き方・精神力に感動し、勇気をもらいました。
スザナもそんな彼女を見て、(テリィ以外の) 自分にとって大切な何かを見つけることができるでしょうか?
キャンディの最終回以降の1920年代は、女性の社会進出が進み、保守的だったキャンディの時代とは違い、いろいろなチャンスや可能性が開けてきた時代です。でも、それを生かせるかはすべてスザナしだい。
マンガや小説にはスザナの精神的な成長を予感させるようなことは描かれていないので、スザナ(とテリィ!)のその後は、ファンがそれぞれ想像するしかないようです。
参考文献
『サラ・ベルナールの一生 本床桂輔 (新潮社)』
『ベル・エポックの肖像 高橋洋一 (小学館)』
『ミュシャ展 華麗なるアール・ヌーボーの世界』
『ベル・エポックの肖像 高橋洋一 (小学館)』
『ミュシャ展 華麗なるアール・ヌーボーの世界』
 雑誌
雑誌
マンガには雑誌のシーンがよく出てきます。最初に出てくるシーンは、ラガン夫人がファッション誌らしいものを読んでいるところ。そのあとはほとんどテリィ関連のゴシップ記事です。
小説によるとパティのお母さんは雑誌記者だそうです。当時のイギリスは女性が社会進出するには難しい時代でした。先進的な女性だったのですね。一度も登場しなくて残念。
<雑誌の創刊年>
生存競争の激しい雑誌業界の中で、創刊100年以上または100年に近い日本でも有名な雑誌が19世紀末〜20世紀初頭に創刊されています。
|
<ゴシップ誌>
女性向けファッション誌『ヴォーグ』(1892年創刊)は、当初はゴシップ誌のようなものでした。セレブ向けですが。
大富豪のヴァンダービルト家の娘がマールボロ公爵と結婚するときに着るドレスや下着などを掲載して話題をよんだそうです。
テリィのゴシップ記事のようなものもあったんでしょうか。
<アパートにあった古新聞・古雑誌>
アルバートさんがベッドの下に隠していたのは、新聞以外に「PLAYS MAGAGINE」・「STAR World」という演劇・芸能系の雑誌でした。
アルバートさんはテリィの記事が気になって買ったのか? それとも単に演劇好き?
 新聞
新聞
当時はテレビもラジオもない時代、一番早く情報が得られるメディアは新聞でした。マンガには戦争の状況を伝える新聞記事が出てきており、第一次世界大戦の開戦時には街で号外が配られていました。
アルバートさんはシカゴのアパートでは毎朝新聞を読んでいた様子。
<新聞の創刊年>
・創刊100年以上のアメリカの新聞・通信社 (日本で有名なもののみ)
|
<当時のジャーナリズム>
19世紀後半から20世紀初頭のアメリカの新聞は、ピューリツァーの「ニューヨーク・ワールド紙」と新聞王ハースト (映画『市民ケーン』のモデル) の「ニューヨーク・ジャーナル紙」の二大新聞の一騎打ち状態で、驚くほどの発行部数を獲得していました。
| 【1913年のニューヨーク紙発行部数】 | ||
| ニューヨーク・ワールド | 85万部 | |
| ニューヨーク・ジャーナル | 70万部 | |
| ニューヨーク・タイムズ | 17.5万部 | |
参考文献 『日本欧米比較情報文化年表 雄山閣出版』
ピューリツァーは金持ちの有力者のものであったジャーナリズムを大衆文化に発展させ、新聞の進歩と新聞人の資質向上に貢献しました。彼の死後にはアメリカ新聞界の最高賞といわれるピューリツァー賞が設立されます。
たくさんの犯罪やスキャンダル等の記事を掲載ときには捏造し、事実報道よりもセンセーショナリズムを売り物にする彼のやり方は「イエロー・ジャーナリズム」と蔑称されました。
しかし、第一次世界大戦ころになるとイエロー・ジャーナリズムは衰退し、大衆は戦争の影響をうけて新聞に真実を求めるようになり、ニュース・報道本位とした道徳的見識を持った真面目な新聞へと急激に変わっていきます。
参考文献 『アメリカ新聞史 ジャパンタイムス』
<新聞に載ってしまったアルバートさん>
小説では、アルバートさんはウィリアムと名乗りでたあと、「シカゴ・ニューズ・エクスプレス」という新聞に正体が出てしまい、記憶喪失の頃の知り合いを驚かしてしまいます。
(アパートのおばさんや聖ヨアンナ病院のレナード副院長など。)
マンガの最後の方で、アードレー家の人たちが「社交界がきっとおおさわぎですわよ」と言ってたりしてますが、社交界や実業界だけではなく、こういうネタはマスコミは大好きなので、テリィのゴシップ記事のようにそうとう派手に載ってしまったのではないかと予想します。
 大衆文学
大衆文学
<赤毛のアン>1908年にモンゴメリが『赤毛のアン』を発表。
カナダの作家なのですが、アメリカのボストンにあるペイジ社から出版。
出版直後からベストセラーとなり、マーク・トウェインをはじめファンレターが殺到した。
モンゴメリはカナダでは女性初の職業作家と言われています。
<ターザン>
1912年にエドガー・ライス・バローズの『類猿人ターザン』が雑誌に掲載され好評を博す。読者からの要望が雑誌社に殺到し続編が掲載されシリーズ化する。1914年に単行本化されベストセラーになる。
テリィがキャンディにつけたあだ名「ターザンそばかす」はけっこうタイムリーなネタを使っていたんですね。テリィは母親に会いにアメリカへ行ったときにでも知ったのでしょうか。
テリィだけかと思ったら、ステアやアルバートさんの会話にも「ターザン」が出てきてました。
「木のぼりだってターザンなみ」、「ラガンさんの岸のターザンの木」など。